2025年8月16日の産経新聞の記事(Yahoo!ニュース配信)によると、グーグルマップに投稿された虚偽の口コミによる名誉毀損を訴えた大阪府内の歯科医師親子の訴訟において、大きな問題が浮き彫りになっています。
大阪地裁は名誉毀損を認め、賠償額26万4千円を認定しましたが、投稿者を特定するための調査費用は50万円以上かかり、結果的に原告側は大きな赤字となりました。
大阪高裁では慰謝料を40万円に増額し、調査費用の半分(27万5千円)を認めたものの、賠償総額は74万2500円にとどまり、依然として費用を賄えませんでした。
ネット中傷が社会問題化する中、こうした「勝訴しても赤字」という構造的問題が、被害者の泣き寝入りを増やす要因となっていると指摘されています。
原告側は、裁判所の賠償額認定の姿勢に危機感を抱き、制度の見直しを求めています。
元記事はこちらです。(https://news.yahoo.co.jp/articles/3e1b0b248fd262dd03b98268e75b2c9f865c2f6a)
Googleマップの虚偽レビューに要注意!裁判費用が慰謝料を上回る実態が!
この記事を読んで、ネット中傷の被害者が直面する現実の厳しさに驚きました。
グーグルマップのような広く使われるプラットフォームでの虚偽の口コミは、個人や事業者の評判を大きく傷つける可能性があります。
しかし、訴訟を通じて正義を追求しようとしても、調査費用や弁護士費用が高額で、勝訴しても経済的な負担が残るという現実は、あまりにも理不尽です。
記事にあった「勝訴しても赤字」という言葉が、この問題の深刻さを象徴していると感じます。
特に、投稿者を特定するための費用が賠償額を上回るケースは、被害者が訴訟をためらう大きな理由になるでしょう。ネット中傷は匿名性が高いため、特定作業自体が時間とコストを要する難題です。
この構造では、泣き寝入りを選ぶ人が増えるのも無理はありません。
Xでの投稿でも、「この構造どうにかならんもんかね」という声や、「名誉回復のための訴訟なのに赤字では」との意見が見られ、ネット上でも同様の問題意識が共有されていることがわかります。 個人的には、プラットフォーム側にも責任の一端があると思います。グーグルマップはユーザーによる口コミを公開する場を提供している以上、虚偽や悪質な投稿への対応を強化すべきではないでしょうか。
記事では、グーグルへの訴訟も進行中とあり、プラットフォームの責任を問う動きに注目したいです。 また、裁判所が調査費用を全額損害として認めるケースが増えつつあるものの、まだ不十分との指摘もあり、司法の判断基準の見直しも急務だと感じます。
かかった費用面をもう少し深堀
記事を読んでみて勝訴しても大きな赤字になる事がある事がわかりましたが、かかった費用についてもう少し深堀をしてみたいと思います。
高額の調査費用
記事では調査費用の詳細については書かれていませんが、金額としては税込55万円とありかつ法律事務所に支払いをしているとあります。
法律事務所側がどこか第三者の調査機関に依頼した可能性はあるとは思いますが、普通に考えると情報開示請求の費用でしょう。
まずはGoogleに対してIPアドレスの開示請求を行い、開示されたらプロバイダが分かりますのでプロバイダに対して個人情報の開示請求を行うという流れかと思われます。
非ホスティング型のサイトの場合は交渉による開示が可能な場合もあり費用は30万~50万円程度に抑えられることもあるようです。
今回のケースが高いのかというと開示請求の標準的な費用範囲(30万~100万円)内に収まっており妥当な水準と言えます。
訴訟費用もかかる
記事では賠償総額として慰謝料40万円と調査費用半額(27万5千円)の合計67万5千円・・・ではなく総額74万2500円とあります。
差額の6万7500円についての記述はありませんので可能性を考えると差額は下記のいずれかでないかと思われます。
・弁護士費用の部分認定
・その他の損害
・利息や遅延損害金
・裁判費用の部分認定
行動前に証拠保全は行うと思いますのでこの場合はグーグルマップの投稿日を起点として遅延利息(3%)の請求は行っていると思われます。内訳は不明なものの+αの認定があるという事ですね。
弁護士費用の一部が認定されている可能性があるのは分かりましたが、調査費用や弁護士費用、訴訟費用の総額80~100万円ほどに達していてもおかしくない事例です。
ネット中傷被害に対する対策は?
ネット社会では、誰もが被害者になり得るこの問題。今回の記事でも何の非もない歯科医院が被害に遭いました。
この問題は自分たちだけ気を付けていても防げない被害という側面が強いです。
弁護士保険という選択
大手損保等が扱う弁護士保険(特約)は対人被害事故または対物被害事故を対象にしてものが多く、今回のようなケースでは保険の対象になりません。
少額短期保険会社の中に業務用の弁護士保険を販売しているところがあり、対応できるのが確認できました。
もう少し調べて追記したいと思います。

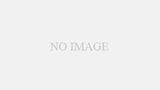

コメント